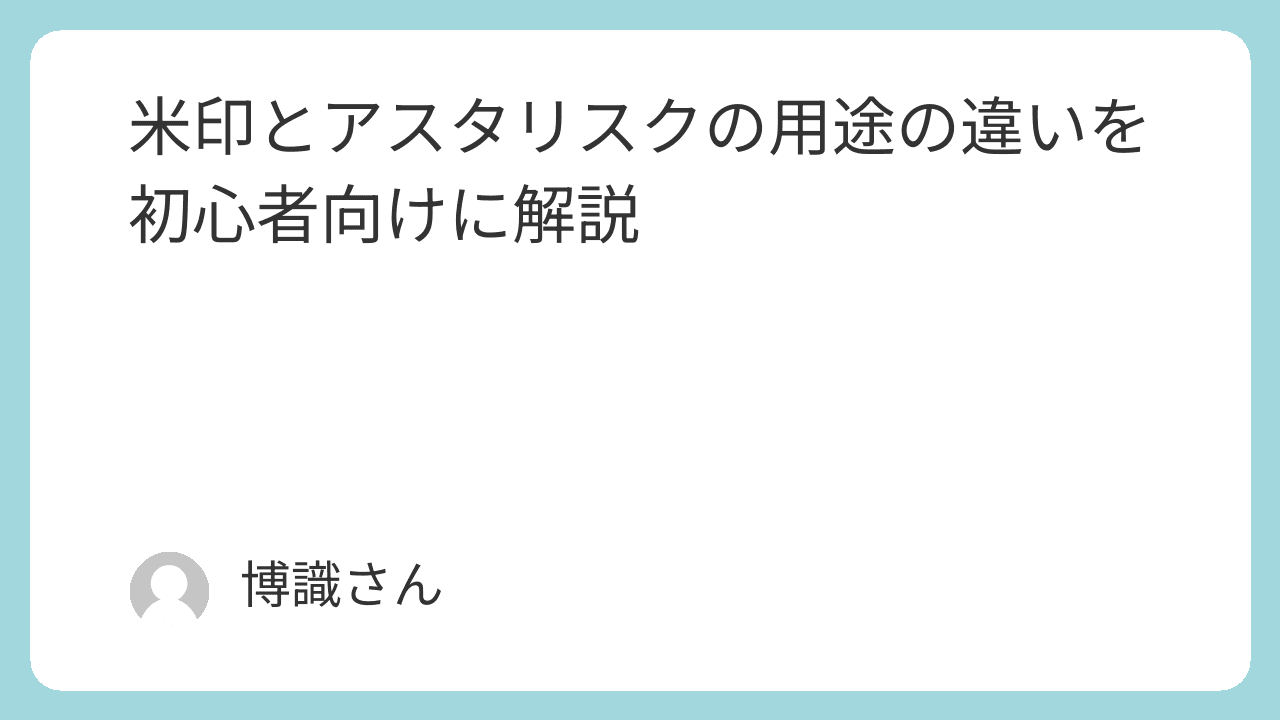文章の中でよく見かける「※(米印)」と「*(アスタリスク)」には、それぞれ違った意味と使い道があります。
この記事では、これらの記号の違いや使い分け方を初心者向けにわかりやすく解説します。
米印とアスタリスクの違いを一言で言うと?

そもそも米印とアスタリスクとは何か?
米印(※)は主に日本語の文書において、補足説明や注意事項、補足情報などを伝えるために使われる記号です。
書籍やパンフレット、取扱説明書など、日常的によく目にする日本語の印刷物で多く見られます。
そのため、日本語の読み書きに慣れている人にとっては、自然と理解されやすい記号です。
アスタリスク(*)は英語圏を中心に使われることが多く、注釈や補足情報に加え、強調、伏字の代用、検索時のワイルドカード、プログラミングにおける演算やコメントの記述など、実にさまざまな用途があります。
このように、アスタリスクは日本語にとどまらず、グローバルな文脈やテクノロジー分野でも広く活用されています。
どちらも注釈記号だけど意味が違う
米印は、日本語の文章の中で「本文の内容に対する補足情報」や「注意書き」として登場することが多く、視覚的にも目立ちやすいため、読者に注意喚起を促す役割を持っています。
たとえば、商品の注意点や限定条件などを強調したいときによく使われます。
一方、アスタリスクは、文章の補足や注釈以外にも、強調の印として単語の両端に使ったり、伏せ字の代わりに使用したり、検索やプログラムで特定の条件に合致する文字列を表す記号としても利用されます。
そのため、用途の幅広さではアスタリスクの方が米印よりも多機能で柔軟に活用できる記号だといえるでしょう。
米印の使い方と意味をやさしく解説

米印の読み方と由来
米印は「こめじるし」と読みます。
この記号は、見た目が米の字に似ていることからその名が付きました。 「米」という漢字が四方に分かれるような構造をしており、その形状と似ていることが由来となっています。
また、日本の文献においては昔から使われてきた記号であり、江戸時代の書物などにも登場することがあります。
つまり、米印は長い歴史を持つ日本固有の注釈記号でもあります。
日本語文書でよく使われる用途
日本語の印刷物や資料、パンフレット、新聞記事、説明書などで、脚注や注意書きを示すためによく使われます。
特に重要な補足や、目立たせたい情報を伝えたいときに活躍します。
たとえば、「※この商品は季節限定です。」や「※数量に限りがあります」など、本文に書ききれなかった情報を伝えるのに便利です。
さらに、文章の途中で注意を促す際にも自然に使うことができるため、読者の理解を深めるサポートとして役立ちます。
アスタリスクの役割と使い道

アスタリスクの読み方と英語圏での使い方
アスタリスクは「asterisk(アスタリスク)」と読みます。
この記号は、英語の文書において非常に多くの用途を持っており、単なる注釈や脚注にとどまらない幅広い役割を果たしています。
たとえば、単語や文の中で特定の部分を強調したいとき、アスタリスクで囲むことによって視覚的なアクセントを与えることができます。
また、不完全な語句や省略された表現に補足を加える際にも使われ、文章の意味を正確に伝えるためのツールとしても活用されます。
たとえば、「he is a *very* good player」のように使えば、「very」の部分が強調されていることが明確になります。
出版物やWebコンテンツ、SNS投稿など、英語圏のさまざまなメディアで見かける記号です。
プログラムやネットでも登場する用途
アスタリスクは、プログラミングやIT分野でも頻繁に登場します。
たとえば、C言語やPythonといった多くのプログラミング言語では、掛け算(乗算)を表す記号として使われます。
また、コメントの囲い記号の一部や、ポインタ変数を表す記号としても重要な役割を担っています。
さらに、ネット検索の場面では、アスタリスクは「ワイルドカード」として使用されます。 これは任意の文字列を表すもので、特定のキーワードの前後に使うことで検索の幅を広げることができます。
たとえば「best * apps」と検索すると、「best free apps」や「best android apps」など、さまざまな組み合わせを含めて検索される仕組みです。
このように、アスタリスクは英語文書やプログラム、検索ツールにおいて、多機能で汎用性の高い記号として重宝されています。
米印とアスタリスクの具体的な使い分け方
注釈・脚注・強調での使い分け事例
紙の書類や日本語の文章では、視認性や読者の読み慣れた形式に配慮して米印が適しています。
たとえば、パンフレットや説明書、店頭ポップなどでは、「※〇〇に限ります」や「※一部地域を除く」のように米印で補足情報を示すのが一般的です。
一方で、英語の論文やWebサイトなど、国際的なコンテンツやデジタルメディアではアスタリスクの使用が多く見られます。
特に複数の注釈を記載する場合には、「*」「**」のように段階的に使い分けることもあります。 また、フォントによってはアスタリスクの方が視認性が高く、画面上でも判別しやすいため、Web文書では優先されやすい傾向があります。
さらに、強調したい単語や文の一部を囲む用途にもアスタリスクは活躍します。
たとえば、SNSやチャットでは「*重要*」のように囲むことで視覚的に強調するテクニックとして使われています。
伏字においても「d***」のように文字を隠す形で活用されており、さまざまな表現方法に対応できます。
ビジネスや文章作成での正しい使い方
社内資料やビジネス文書で補足情報を示す際には、日本語の慣習に沿って米印を使用することで、読み手に安心感と信頼感を与える効果があります。 特に公的な資料や報告書では、米印を用いた注釈の記載が好まれる傾向があります。
一方、外資系企業や多言語対応資料など、英語が含まれる文書やグローバル向けのコンテンツにおいては、アスタリスクを使用する方が一般的です。
WordやPowerPointなどのビジネスソフトでも、注釈機能のマークとしてアスタリスクがデフォルトで設定されていることが多く、その流れに沿った使い方が推奨されます。
文書の受け手や用途に応じて記号を使い分けることで、より伝わりやすく、洗練された印象の文書に仕上げることができます。
米印とアスタリスクの入力方法
パソコン・スマホでの簡単な入力手順
パソコンでは、米印(※)を入力するには、ひらがなで「こめ」と打ち、変換キーを押すと一覧に米印が表示されます。
通常の日本語入力環境(IME)であればすぐに変換候補に出てくるため、難しくありません。
アスタリスク(*)は、「け」のキーをShiftキーと同時に押すことで入力できます。 「*」という記号は英語入力モードでも日本語入力モードでも同じ操作で入力可能です。
スマートフォンの場合、米印は日本語キーボードを使用して「こめ」と入力し、変換候補から選ぶことで簡単に入力できます。
一部のスマホでは、記号の一覧に含まれていることもあるため、記号キーボードを表示して探すのも一つの方法です。
アスタリスクは、英語キーボードや記号一覧にあるため、記号タブを開き「*」をタップすることで入力できます。
アプリによっては、長押しメニューやショートカットで素早く入力することも可能です。 環境に応じて、入力のしやすい方法を選びましょう。
まとめ
米印とアスタリスクは、どちらも補足や注釈を示すための記号ですが、使われる場面や意味には違いがあります。
日本語文書での注釈には米印、国際的な用途や強調にはアスタリスクと、シーンに応じて使い分けることが大切です。